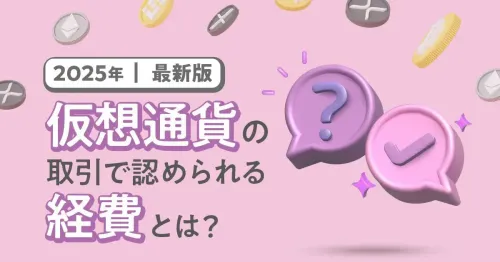仮想通貨(暗号資産)取引で大きな利益を上げたとしても、税金の問題を考慮しないと、その利益が大幅に減少する「税金地獄」に陥る可能性があります。特に、所得税及び住民税の最高税率が55%にも達する日本では、この問題は避けて通れません。
この記事では、仮想通貨(暗号資産)取引から得た利益にかかる税金の仕組みと、それを効率的に節税する具体的な方法について詳しく解説しています。所得税の雑所得としての確定申告の必要性、税金の計算方法、経費の計上による税負担の軽減、さまざまな税控除の活用方法など、税金地獄を回避し、より多くの利益を手元に残すための実用的なアドバイスが満載です。
目次 |
仮想通貨(暗号資産)の税金に抜け道はある?
「抜け道」と聞くと、課税を逃れる“裏技”や、場合によっては違法すれすれの手段を思い浮かべる方もいるかもしれません。
しかし、支払うべき税金から不当に逃れる行為、すなわち意図的な無申告や過少申告は脱税行為であり、絶対に避けなければなりません。
そもそも世間一般で言われる「節税」とは、不当に税額を少なくすることではありません。公に認められた方法を使って合法的な形で税額を最適化することをいいます。
例えば、損益の最適化や経費の計上、各種所得控除の活用などです。つまり、「抜け道」というよりも税金の「正しいルート」を知ることが、結果的に税負担を減らす近道となるのです。
確定申告の必要あり!所得税の「雑所得」で申告
仮想通貨(暗号資産)で得た所得は所得税の課税対象
仮想通貨(暗号資産)で得た利益は、所得税の対象となります。特に、会社員の場合は年間で20万円以上の利益を上げた場合、確定申告が必須となります。
この利益は「雑所得」として申告されるのが一般的です。雑所得とは、給与所得や事業所得以外の所得のことを指し、賞金や年金、不労所得もこのカテゴリーに含まれます。仮想通貨(暗号資産)の利益も、これに該当するため、雑所得として申告する必要があります。雑所得として分類される理由は、仮想通貨(暗号資産)取引が一般的な給与所得や事業所得とは異なる性質を持つからです。具体的には、仮想通貨取引は個々の取引によって利益や損失が発生するため、その計算が複雑であり、一般的な所得のカテゴリーには当てはまらないのです。
仮想通貨(暗号資産)の税率
上述の通り、仮想通貨(暗号資産)で得た利益は「雑所得」として扱われます。雑所得は「総合課税」の対象となり、他の所得(例えば、給与所得など)と合算されて課税されます。これは特に会社員の方に影響を与える点であり、給与と仮想通貨(暗号資産)の利益が合算されるため、全体の税率が高くなる可能性があります。
<所得金額と税率>
これに加えて、住民税が10%かかります。したがって、最高税率は所得税45%+住民税10%で合計55%となります。
仮想通貨(暗号資産)で得た利益もこの税率に基づいて課税されます。例えば、仮想通貨(暗号資産)で年間1,000万円の利益を上げ、その他の所得(給与など)で2,000万円ある場合、合計の3,000万円が所得として計算され、そこから社会保険控除などの所得控除項目が控除されて課税所得が算出されます。その課税所得を上記表に照らして所得税の税率が適用されます。さらに10%の住民税が加わることとなります。
このように、仮想通貨(暗号資産)の税率は総合課税によって所得全体と合算されて計算されるため、その他の所得が多い場合は、仮想通貨(暗号資産)での利益にも高い税率が適用される可能性があります。
なお、仮想通貨(暗号資産)の税金についてはこちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
税金が発生するタイミング
仮想通貨(暗号資産)取引における税金の発生タイミング、すなわち利益が発生するタイミングであり、「利益が確定したタイミング」です。
例えば、仮想通貨(暗号資産)を日本円に換金したとき、あるいは別の仮想通貨(暗号資産)に交換したり、商品・サービスの購入に仮想通貨(暗号資産)を使用したときなどが該当します。
また、マイニングやステーキング報酬、エアドロップなどで仮想通貨(暗号資産)を受け取った時も「所得」として認識されます。
実際に日本円を手にしていなくとも、時価レートで日本円換算した金額の分だけ所得が発生したと見なされ、課税対象となります。
こうした仮想通貨(暗号資産)取引において損益認識されるタイミングについて詳しく知りたい方は関連記事もあわせてご覧ください。
仮想通貨(暗号資産)の税金未納がバレたときのペナルティ
仮想通貨(暗号資産)の利益があるにもかかわらず、正しく申告せずに放置すると、後に発覚した際に重いペナルティを課されることになります。
例えば、確定申告で申告した所得金額が実際より少なかった場合は、最大15%の「過少申告加算税」が追徴課税に加算され、確定申告そのものを怠った場合は、最大30%の「無申告加算税」の対象となります。
また、納税が遅れた期間に応じて「延滞税」が加算されることから、追徴課税の金額は想像以上に大きく膨らむと考えた方が良いでしょう。
なお、未納に加えて仮装・隠蔽などの悪質性が認められる場合は、更に重たい「重加算税」の対象になる可能性があるほか、場合によっては脱税によって逮捕される可能性もあります。
税金未納のペナルティについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
仮想通貨(暗号資産)の税金を減らす(節税)方法一覧
仮想通貨(暗号資産)の所得に対する税金を減らす方法
①取引にかかる経費を計上し、利益を減少させる
仮想通貨(暗号資産)取引には、取引手数料やウォレットの維持費など、さまざまな経費が発生します。これらの経費を計上することで、課税所得が減少し、結果的に支払う税金も減ります。例えば、年間で100万円の利益を上げたとします。その際に10万円の取引手数料が発生した場合、この10万円は経費として計上できます。その結果、課税所得は90万円となり、税金もそれに応じて減少します。
このように、経費をしっかりと計上することで、実際に支払う税金の額を減らすことが可能です。どんなコストが経費計上できるのか知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
②含み損益を把握して適切な売買をする
含み損益を把握することは、仮想通貨(暗号資産)取引での節税に大きく寄与します。
含み損がある場合、その仮想通貨(暗号資産)を売って損失を確定させれば、他の仮想通貨(暗号資産)の利益と相殺できて全体の課税所得が減ります。
逆に、大きな含み益がある場合はその売却のタイミングを翌年以降へ調整することで、利益の繰り延べ(課税の先延ばし・分散)が可能です。
この際、所得税の税率を考慮に入れることが重要です。例えば、他の所得が少ない年には、大きな利益を確定させても累進課税の影響を受けにくいためです。
このように、含み損益をしっかりと把握し、それに基づいて戦略的な損切りや利確を行うことで、最終的な税負担を減らすことが可能なのです。
詳しくはこちらの記事も併せてご覧ください。
③仮想通貨(暗号資産)同士の損益通算を利用する
雑所得は通常、その他の所得と相殺することはできませんが、仮想通貨(暗号資産)同士の場合は例外です。仮想通貨(暗号資産)で得た利益と別の仮想通貨(暗号資産)で発生した損失は相殺可能です。この特例を利用することで、全体の課税所得が減少し、税金も相応に少なくなります。例えば、ビットコインで100万円の利益を得た一方で、イーサリアムで50万円の損失があった場合、この二つを相殺し課税所得は50万円となります。
このように価格変動リスクを逆に活かし、仮想通貨(暗号資産)同士の損益通算を利用することで、税負担を軽減することが可能です。ただし、この手法を採る際は、確定申告で損益を正確に計算し報告する必要があります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
④法人成りによる節税をおこなう
仮想通貨(暗号資産)取引による利益が多い場合、法人を設立して取引することで税率を下げる方法もあります。法人税の税率は、所得税よりも一般的に低いため、有効な手段です。具体的には、法人を設立することで、最高法人税率が25.5%となり、個人の最高税率55%と比べても大幅に税負担を軽減することが可能です。このような理由から、仮想通貨(暗号資産)による利益が大きい場合は、法人設立を検討する価値があります。
ただし、法人化するには仮想通貨(暗号資産)を法人に譲渡するなどの手続きが必要になりますし、固定費などのデメリットも多くかかってきます。法人化することで得られるメリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
法人化することで得られるメリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
併せて利用したい所得全体を減らす方法
①青色申告の適用を検討する
青色申告は、主に個人事業主が利用する確定申告の方法となります。青色申告を行うことによってと、一定の経費控除が受けられ、税負担を軽減できます。
具体的には、青色申告を選択することで、65万円の一律控除が受けられます。この控除を活用することで、課税所得を減らし、税金を節約することができます。
ですが、仮想通貨(暗号資産)取引を青色申告の対象にするためには、帳簿保存や年間の仮想通貨取引量、社会通念上の判断などの各種要件が必要となりますので、留意が必要です。
②ふるさと納税や各種税控除を利用する
ふるさと納税を利用すると、その分だけ所得税が減少します。具体的には、ふるさと納税で寄付した金額が、所得税および住民税から控除されます。
また、生命保険料控除や住宅ローン控除など、他にも多くの税控除が存在します。これらをうまく活用することで、全体の税負担を軽減することができます。例えば、年間で100万円の利益を上げた場合でも、これらの税控除を活用することで、実際に支払う税金を大幅に減らすことが可能です。
③iDeCo・小規模企業共済など節税制度を活用
仮想通貨(暗号資産)取引の利益が大きくなった年は、課税所得も増加し、税負担が重くなります。そこで活用したいのが、iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済といった所得控除制度です。
iDeCoは私的年金の一種で、自分で決めた掛金を毎月納めることで資産運用をし、老後に年金方式で受け取れるという制度です。
一方、小規模企業共済は小規模企業の経営者や個人事業主などが使える積立による退職金制度です。
これらの掛金は全額が所得控除の対象となるため、課税所得を圧縮することで結果的に支払う税額を抑えることが可能です。
将来の備えをしながら節税にもつながるため、特に企業経営者や個人事業主の方が仮想通貨(暗号資産)取引を行っている場合には有効な選択肢と言えるでしょう。
④配偶者控除・扶養控除の最適化
所得が48万円以下であるなど一定の条件を満たす配偶者や家族がいる場合、配偶者控除(最大38万円※)・扶養控除(38万円)や特定扶養控除(63万円)を活用できます。
※納税者本人の合計所得金額が900万円以下で配偶者が70歳未満の場合
ただし、配偶者や扶養対象の家族が仮想通貨(暗号資産)取引で副収入を得て、その年の所得が48万円以上になると、控除の対象から外れる可能性があります。
その結果、仮想通貨(暗号資産)取引を行った当人の税負担が発生するだけでなく、配偶者控除・扶養控除を利用していた人の税負担も増えることになりかねません。
控除を最適に活用するには、家族の年間所得や仮想通貨(暗号資産)の利益確定タイミングを事前に把握し、世帯全体の課税所得を抑えるように、取引や確定申告を戦略的に調整することが大切です。
減らす以外の方法
⑦利益確定は年間20万円以下に抑える
会社員で年末調整を実施済みの方は、年間で20万円以下の利益を上げた場合、確定申告は不要となります。このルールは、年間取引利益が20万円以下の人に限ります。それ以上の利益がある人は、その分が課税されます。この制度を利用するためには、年間の取引での利益を20万円以下に抑える計画性が必要です。
仮想通貨(暗号資産)の損益計算は、総平均法(1年間の購入平均レートをもとに計算した取得価額の合計と、売却合計金額の差額(所得)を計算する方法)を用いて計算するため、利益が実感と異なる場合があります。複雑な計算を正確かつ自動化させたいとお考えの方は、損益計算ツールを活用するのがおすすめです。中でも「クリプタクト」は1分単位で通貨の価格を取得しているためリアルタイムで実現損益を確認できます。無料のプランもあるため気になる方は登録してみましょう。
まとめ
仮想通貨(暗号資産)取引で得た利益は確定申告が必要であり、多額の利益を得た場合は税率が非常に高くなってしまう可能性があります。しかし、上記のような対策を行うことで税金地獄を回避し、より多くの利益を手元に残すことが可能です。
当サイトでは仮想通貨(暗号資産)の税金に関する情報や最新のトレンドワード解説などの記事を随時掲載しています。最新情報を知りたい方はメルマガの登録してみてください。