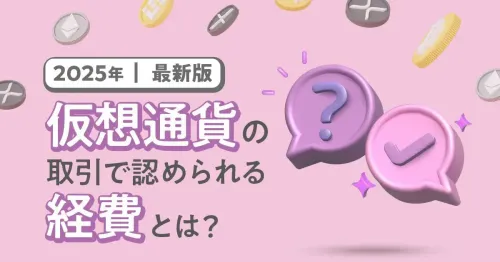仮想通貨(暗号資産)取引を続ける中で、「個人事業主として申告すると税金はどうなるのか?」と気になっていませんか?
仮想通貨投資で個人事業主として開業した場合、節税の選択肢が大きく広がる可能性があります。一方で税率の仕組みや経費の計上ルールなど理解しておくべきポイントが多くあります。
この記事では、個人事業主として仮想通貨取引を行う際の税金の基本知識や節税の仕方、申告時の注意点などについてわかりやすく解説していきます。
目次 |
仮想通貨(暗号資産)投資で個人事業主として開業するには
個人事業主として開業する際の手続きは、「個人事業の開業・廃業等届出書」(通称、開業届)と呼ばれる書類を税務署に提出するだけで、開業の手続きは完了します。
ただし、個人事業主であっても全ての利益が一律に税制上有利な「事業所得」となるわけではありません。利益が「事業所得」として認められずに「業務に係る雑所得」と見なされてしまうと、税制上のメリットの多くが失われてしまいます。
仮想通貨投資で個人事業主として開業する場合、仮想通貨投資による利益が「事業所得」として認められるための条件を満たしていることが重要となるのです。
仮想通貨取引を事業所得に計上する際の条件
仮想通貨取引で年間300万円超の収入があること
仮想通貨取引による収入を事業所得として計上するためには、取引を事業と称するに値する規模で行っている必要があります。
国税庁が公開している資料「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」によると、年間の収入が300万円超であることが事業所得として計上する際の目安とされています。
仮想通貨取引による収入がこの水準を超えるときは、事業所得としての申告を検討してみるとよいでしょう。
開業届・青色申告承認申請書などの書類を事前に税務署へ提出していること
仮想通貨取引による収入を事業所得として計上するためには、事業と称するに値する規模で取引を行っている必要があります。
また、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰越控除(3年間)などの税制優遇を受けるためには、事前に青色申告承認申請書の提出も必要です。
青色申告承認申請書の提出期限は青色申告を適用したい年の3月15日まで(もしくは開業から2カ月以内)となっていますので注意しましょう。
記帳・帳簿書類を保存していること
仮想通貨取引による収入を事業所得として申請するためには、取引を適切な方法で記帳した帳簿書類を作成・保存しておく必要があります。
帳簿書類が整っていない場合、仮に年間収入が300万円超であっても、また開業届を提出していても、原則として事業所得として認められずに雑所得の扱いとなってしまいます。
適切な帳簿の有無は、事業所得と認められるための非常に重要な判断基準となっているのです。
事業としての社会通念上の概念を満たしていること
上記のほかにも、仮想通貨取引が事業として認められるためには「社会通念上、事業と称するに至る程度」で行われているかどうかも判定要素になります。
つまり、事業性の有無は必ずしも形式的な基準だけで判断されるのではなく、社会通念を踏まえた実体的・総合的な判断も加味されるのです。
具体的には、社会通念上の概念の判断基準として以下のような事項が検討されることとなります。
- 仮想通貨取引で年間300万円超の収入があること
- 開業届・青色申告承認申請書などの書類を事前に税務署へ提出していること
- 記帳・帳簿書類を保存していること
- 事業としての社会通念上の概念を満たしていること
このうち、社会通念上の概念については、実質的な判断となっています。
具体的には、社会通念上の概念の判断基準として以下のような事項が検討されることとなります。
社会通念上の概念の検討事項事例
- 営利性があるか
- 有償性があるか
- 継続性、反復性があるか
- 自己の危険と計算における企画遂行性があるか
- 費やした精神的あるいは肉体的労力があるか
- 人的、物的資本があるか
- その他、取引目的、職歴、社会的地位、生活状況なども考慮し、その人にとって事業としてふさわしいか
なお、国税庁では「事業所得」として申告できる所得について、次のような判断基準を設けています。

※資産の譲渡は譲渡所得・その他所得
(注)次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
①その所得の収入金額が僅少と認められる場合
②その所得を得る活動に営利性が認められない場合
引用:国税庁|「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
上記の表では、「収入金額」と「記帳・帳簿書類の保存有無」が判断軸とされていますが、中でも特に「記帳・帳簿書類の保存」が重要な要素となっていることが伺えます。
つまり、「記帳・帳簿書類の保存」を行っていれば概ね事業所得であると考えられ、「記帳・帳簿書類の保存」をしていない場合は、年間収入が300万円を超えているか否かで事業所得にできる可能性の有無が決まる形になっているのです。
さらに、事業として認められるかについての実質的な判断として、社会通念上の概念を満たしているかどうかの判断がされる仕組みになっています。
ページ下部の関連記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
なお、会社員の方や別の事業で個人事業主として事業をされている方が仮想通貨取引で利益を得た場合、その利益は原則として「雑所得」に分類され、総合課税の対象となります。
これは、会社員や個人事業主の収入が本業の収入と判断され、社会通念上の概念を満たすことが原則として難しいと判断されるためです。
個人事業主の税金と課税の仕組み
会社員の方や別の事業で個人事業主として事業をされている方が仮想通貨取引で利益を得た場合、その利益は原則として「雑所得」に分類され、総合課税の対象となります。総合課税では、所得が多いほど税率が高くなる仕組み(累進課税)が採用されています。
所得税の場合、最高で45%の税金がかかります。さらに雑所得は住民税(10%)・復興特別所得税(所得税額×2.1%)の対象となるため、所得税と合わせると税率は最高で55.945%にの税率になります。
実は、個人として「雑所得」とする場合も「事業所得」とする場合も総合課税の対象となるため具体的な税率自体は同じです。
ではどうして仮想通貨取引を事業として扱うことが税金対策につながるのでしょうか。
ここでは「雑所得」と「事業所得」の違いと、税制上メリットとなる仕組みを簡単に説明します。
「雑所得」だとできない損益通算や繰越控除が可能に
「事業所得」には、課税所得額を低く抑えるための選択肢が幅広く用意されています。
仮想通貨の利益を「雑所得」で申告している場合、損益通算や繰越控除を利用できません。損益通算とは、他の所得との利益と損失を相殺する仕組みです。たとえば、仮想通貨取引で赤字が出た場合、その損失を他の所得から差し引いて、課税される金額を減らすことができません。
また、繰越控除も「雑所得」では適用されません。繰越控除は、今年の損失を翌年以降の利益と相殺することで、長期的な税金の負担を軽減できる仕組みですが、雑所得ではこれができないのです。
一方、「事業所得」として仮想通貨取引を申告すると、損益通算が可能になり、他の所得(不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得が対象。一部例外有。)と相殺することができます。さらに、下記の青色申告を満たすことで、繰越控除も利用できるため、今年の損失を翌年以降の利益と相殺することで、長期的な税金対策にもつながります。
青色申告でさらに税制上の優遇を受けることができる
もし仮想通貨取引を事業として扱い、「青色申告」を選択すると、さらに税制上の優遇を受けることが可能です。青色申告を行うことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。これは課税所得が最大65万円控除(減額)されることを意味しますので、非常に大きな節税効果があるのです。
仮想通貨(暗号資産)取引で開業した場合の税金対策
それでは、個人事業主として仮想通貨取引にて開業した場合にできる税金対策について、より具体的に見ていきましょう。
経費を正確に算出して収入から差し引く
仮想通貨取引による利益が「雑所得」「事業所得」のどちらであろうとも、経費を漏らさず正確に計上することは、最も手軽に始められる節税方法のひとつです。
所得税は収入から経費などを引いた課税所得に対して税率を掛けて算出されるため、所得を低く抑えることが重要となります。
ただし、仮想通貨取引において経費に該当するのは、仮想通貨の売買などに際して直接要した費用となります。
個人事業主が経費にできるものの具体例
具体的には、以下のようなものが経費として計上できる可能性があります。
|
なお、電気代や通信費など、仮想通貨取引以外の用途と共用している場合は按分計算が必要です。個人事業主として自宅で仮想通貨取引を行う場合などは、特に注意するようにしましょう。
また、パソコン代については10万円以上の場合は減価償却の対象となるため、一括で経費計上することができません。ただし、青色申告書を提出して少額減価償却資産の特例を受けることができる場合は、30万円以上が減価償却の対象となります。仮想通貨取引における経費計上についてはページ下部の関連記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
事業所得について青色申告を行う
確定申告の際に青色申告を選択することで、税制面でさまざまな優遇措置を受けることができます。
青色申告とは、開業届を提出していて一定の条件を満たした人が選択できる申告方式のことです。最大65万円の青色申告特別控除が受けられるため、課税所得を大幅に圧縮することができるほか、最大3年間に渡って赤字を繰り越すことができるようになり、利益が不安定な仮想通貨取引においては長期的な視点で非常に有効な節税手段となります。

比較表(pafin作成)
また、仮想通貨取引による利益を事業所得として計上することで、雑所得よりも経費の範囲が相対的に増えるため、経費計上できる費用が増える点もメリットと言えるでしょう。
なお、青色申告は白色申告の場合と比べて確定申告の内容が複雑になるほか、記帳や帳簿書類の保存などの要件が厳しくなる点はデメリットとなります。会計ソフトなどを導入し、仮想通貨取引の税金計算などの管理負担を可能な限り軽減させる工夫をすることが重要でしょう。 現在の主要な会計ソフトは基本的に複式簿記に対応しているため、会計ソフトを導入し、会計ソフトにしっかりと入力すればそれだけで概ね青色申告の要件を満たすこととなります。
法人化を検討する
仮想通貨取引で一定以上の所得を得ている場合は、「法人成り」すなわち事業の法人化を視野に入れてみるのも一つの方法です。
法人化するメリット
法人化する大きなメリットの一つが、税金が安くなる可能性があることです。
個人の場合は所得額に応じて5%〜45%の所得税および10%の住民税がかかりますが、法人の場合は所得税の代わりに15%〜23.2%の法人税がかかります。
住民税や法人住民税・法人事業税などを加味しても個人より法人の方が最大税率が低いため、収入が一定水準を超える場合は法人化した方が税金面で有利になるのです。
また、法人化することで経費に計上できる範囲が個人事業主より広がる点もメリットです。個人事業主は「生活との区別」が厳しく求められますが、法人は会社としての支出であれば幅広く経費計上が認められる傾向にあります。
法人化するデメリット
一方で、法人化にはデメリットも存在します。
個人事業主が開業届を提出するだけで始められるのに対して、法人は設立時に登記などの費用が必要になります。また、法人の経理や決算事務なども発生するため、個人事業主よりも事務が煩雑になる点にも考慮が必要です。
特に仮想通貨に関しては、法人は原則として期末時価評価の実施が必要です。期末に保有するすべての仮想通貨を時価評価し、簿価の洗替処理をします。法人は個人とは異なり、含み益に対しても課税されるのです。
こうした管理作業をすべて手作業で行うのは大変負担が大きいため、仮想通貨の管理に長けた会計ツールを導入するなど、事務の効率化も併せて検討する必要があるでしょう。
法人化したほうが良いケース
おおよその目安として、個人事業の課税所得額が800万円を超えると法人化のメリットが大きくなってくると言われています。
所得800万円の場合、所得税率が23%であるのに対して、法人税は15%です。住民税や法人事業税、法人の維持コストなどを加味しても法人の方がコスト面で有利になる可能性がでてくるのが、このあたりと考えると良いでしょう。
また上記に限らず、将来の事業拡大を視野に入れる場合は早期に法人化するのも良いでしょう。
法人化せずに個人事業主のままが良いケース
一方で全ての人が法人化した方がよいわけではありません。
たとえ仮想通貨取引の利益が800万円を超えていても、それが一過性の利益である場合は、法人化することで翌年以降の負担が重くなってしまう可能性も考えられます。
小規模で、コストをかけずに仮想通貨取引を行いたい場合は、個人事業主のままで続けることも有力な選択肢と言えるでしょう。
個人事業主が仮想通貨(暗号資産)取引の利益にかかる税金を抑えるには?
上述のとおり、経費を計上することや含み損益を把握して適切な売買をすることなどがあげられます。
以下の記事で詳しく紹介していますので併せてご覧ください。
仮想通貨の税金対策ならクリプタクトがおすすめ!
この記事では、仮想通貨取引にかかる税金を安くするための対策について解説してきました。
特に仮想通貨取引を事業として行うことで、個人事業主または法人として大きな節税につながる可能性があります。
ただし、仮想通貨取引の税金を申告する際には、年間の取引履歴を全て漏らさず把握し、正確な損益計算に基づいて税額を算出する必要があります。
ただでさえ手作業で行うのは負担が大きい作業ですが、さらに青色申告や法人決算などの負担も重なる場合は、出来る限り仮想通貨の計算作業を自動化して、作業負担を軽減することが欠かせません。
仮想通貨専門の損益計算ツール「クリプタクト」であれば、確定申告に必要な仮想通貨取引の損益計算を簡単に自動化することが可能です。
実現損益と年度損益も同時に見比べることができるため、最適な税金対策を検討するうえで必要な情報にいつでもアクセスすることができます。

※実現損益の表示は有料プランでのみ可能です。
また、法人化した際に必要となる年度末評価損益の加算に関する機能もが備わっているため、法人における仮想通貨の期末会計処理もサポートすることができます。

※法人評価損益機能はProプラン以上で可能です。
これらの計算に必要な仮想通貨の取引履歴は、国内外における多数の仮想通貨取引所とのAPI連携や、ブロックチェーンからの取引履歴取得機能により、DeFi取引を含めて幅広い対象を手間をかけずに収集できます。
「クリプタクト」を活用することで煩雑な確定申告作業をできる限りシンプルにして、効率的に税金の対応を進めてみてはいかがでしょうか。
「クリプタクト」は取引量に応じたプラン設定となっていますので、無料のFreeプランで上記すべての機能がご利用いただけます。この機会にぜひお試しください。